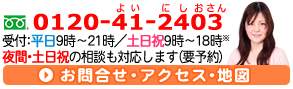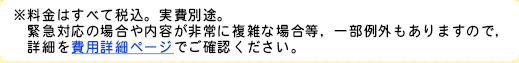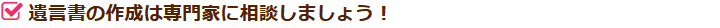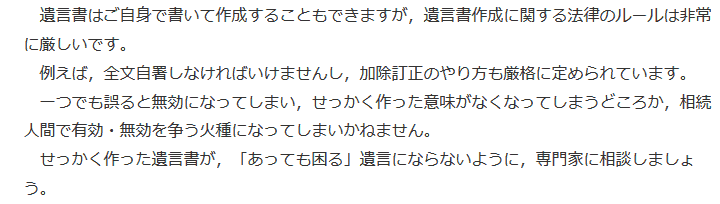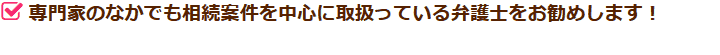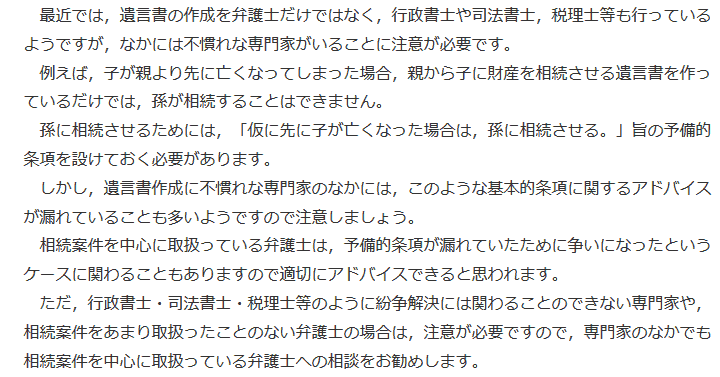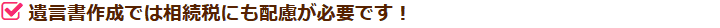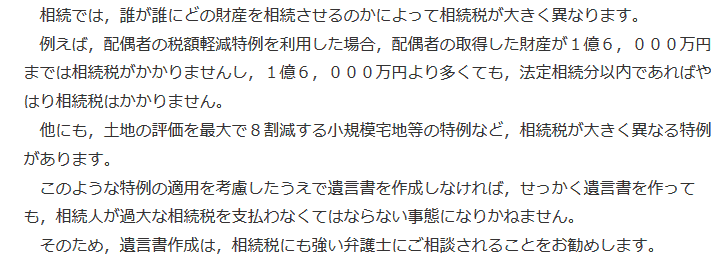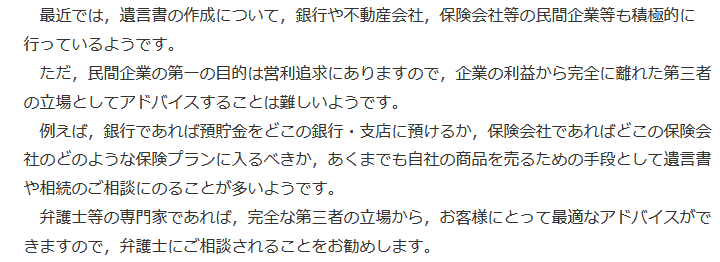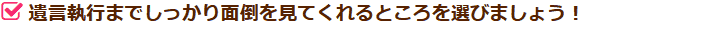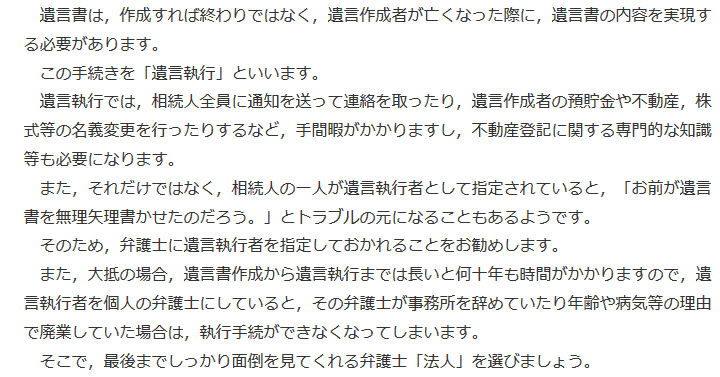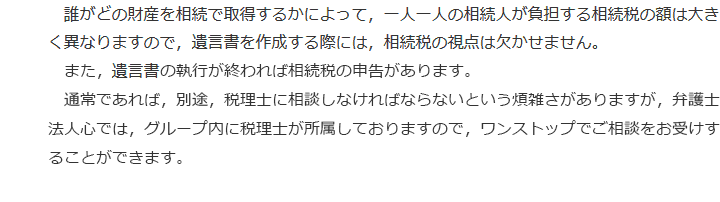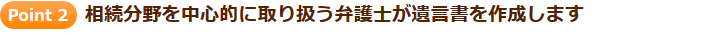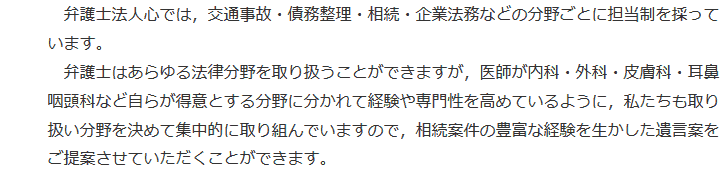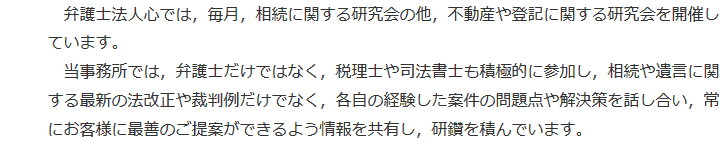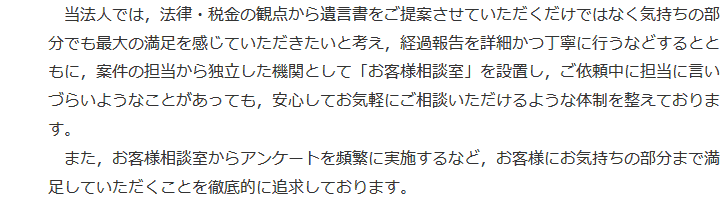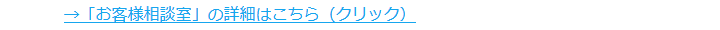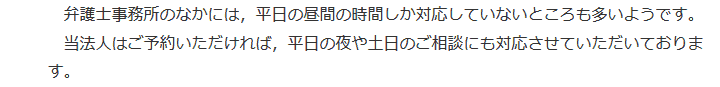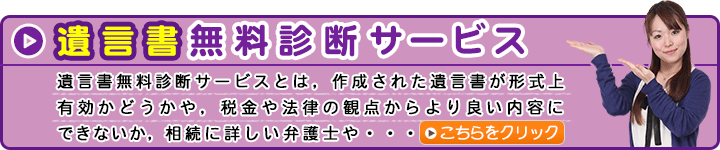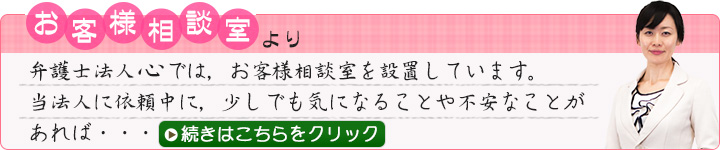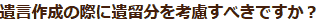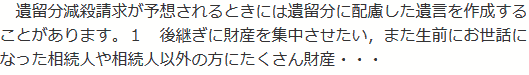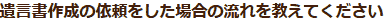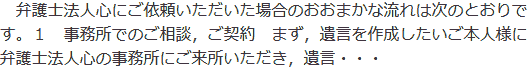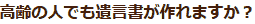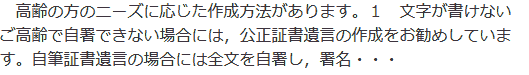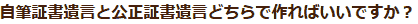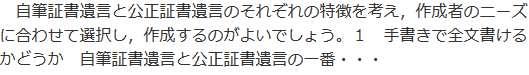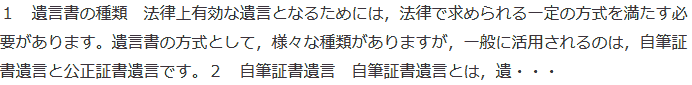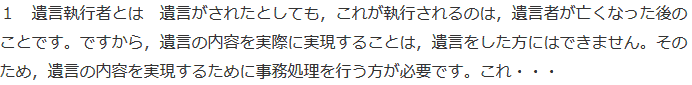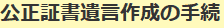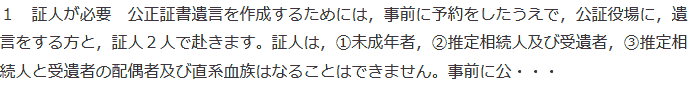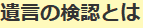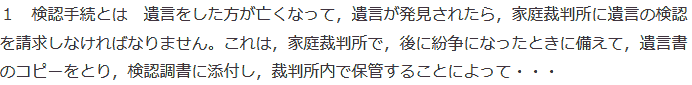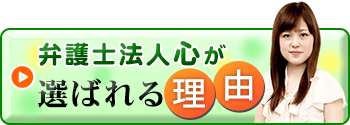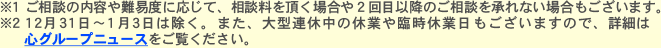相続人が揉めない遺言を作成するためのポイント
1 遺言を作成するメリット
遺言を作成するにあたっては、作成時にいくつかのポイントを押さえることで、相続発生後に相続人同士が揉めることを回避できる可能性は高くなります。
ここでは、揉めない遺言を作成するためのポイントをいくつかご説明いたします。
2 遺留分に配慮する

遺留分とは、相続人(兄弟姉妹は除く)の一部に認められた遺産に対する権利のことをいいます。
遺言者が遺言書において、遺産を特定の相続人に相続させた場合でも、当該遺言書に従った相続を行うことで別の相続人の遺留分が侵害されるときには、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額に相当する金額の支払いを請求することができます(民法第1046条第1項)。
遺留分の計算の仕方について、遺留分権利者全体の遺留分の割合というのは、民法で決まっています。
直系尊属人のみが相続人である場合には遺産全体に対する3分の1、それ以外の場合には2分の1となっています。
この遺留分権利者全体の遺留分の割合に各相続人の法定相続分を乗じることで、各相続人の遺留分割合を算出することができます。
遺言を作成する場合には、できるだけ各相続人の遺留分を侵害しないように配慮する必要があります。
遺言者が、一方の相続人の遺留分に配慮せず、他方の相続人にのみ遺産を相続させてしまうと、相続発生後に遺留分をめぐって相続人間でトラブルが生じる火種となりますので注意が必要です。
3 遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言内容を実現するための手続きを行う人のことをいいます。
遺言を作成するうえで、遺言執行者の指定は遺言の要件となっていません。
しかし、相続人間で対立が生じている場合、たとえ遺言を遺したとしても、その遺言内容を誰が執行するかをめぐってまた争いになる可能性があります。
せっかく遺言書を作成しても、遺言の内容が実現されないのではいわゆる絵に描いた餅となってしまいます。
相続人間での対立が予想され、遺言内容の実現に不安を覚えられる場合には、あらかじめ遺言執行者を定めておくことをおすすめします。
4 付言事項
付言事項とは、遺言書において法的効果が与えられない記載事項のことをいいます。
遺言者の生前の気持ちや家族への感謝のメッセージのほか、遺言書で定めた事項についてなぜそのような記載をしたのか理由を書く場合もあります。
付言事項には法的効力が与えられるものではないのですが、付言事項を書くことによって遺言者の真意を相続人により伝えやすくすることができ、場合によっては相続人間の対立を和らげて相続発生後の相続人間のトラブルの防止に役立てることができることもあります。
遺言の作成に必要な費用
1 遺言の種類

遺言には、大きく自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
このうち、一般的に多く用いられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者(遺言で自分の財産の取得先を決める人)が、文字どおり自筆で書く遺言です。
なお、財産目録は、該当ページに署名押印をすることで、ワープロ等で作成することも認められています。
公正証書遺言は、公証役場において、公証人が作成する遺言です。
どのような内容の遺言を作成するか、下書きなどを提供し、公証役場が清書を行ったうえ、公証人と遺言者とが対面で意思確認を行って作成されます。
自筆証書遺言も、公正証書遺言も、遺言としての法律上の効力は同じです。
もっとも、上述のとおり、作成に必要な作業の内容や、関わる人・期間が大きく異なります。
そのため、必要な費用も異なります。
以下、それぞれの費用について説明します。
2 自筆証書遺言の費用
自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑さえあれば、基本的には遺言者だけで作成することができます。
そのため、もし遺言者ご自身ですべて作成する場合には、費用はほとんどかかりません。
もっとも、自筆証書遺言は、法律によって形式が厳格に決められています。
形式に間違いがあると、無効になってしまうこともあります。
また、形式不備はなく、法律上は有効であっても、不動産や預貯金についての記載の仕方によっては、登記の際に法務局が応じてくれなかったり、銀行が預貯金の名義変更に応じてくれなかったりするなど、実務上の不都合が生じることもあります。
そのため、弁護士などの専門家に原稿作成を依頼し、法律上も実務上も問題のない内容の遺言案を作成してもらい、自筆に起こすというプロセスをとった方が確実です。
専門家に依頼する費用は、財産の種類や、相続・遺贈の割振りの複雑さにもよりますが、一般的には数万円~十数万円程度です。
3 公正証書遺言の費用
公正証書遺言は、遺言に記載したい内容を公証役場に提示し、公証役場で清書してもらったうえで、証人2人の立ち合いのもとで、公証人と対面で作成します。
遺言に記載したい内容の作成、公証役場とのやり取り、証人の手配などをすべて自身で行う場合は、公証役場の費用のみが必要になります。
遺言に記載する財産の評価額によって費用は変わりますが、一般的には数万円~数十万円です。
しかし、遺言に記載したい内容の作成、公証役場とのやり取り、証人の手配も、経験がない方にとってはとても大変です。
そこで、弁護士などの専門家にこれらの対応を依頼することができます。
その場合、上述の公証役場の費用のほか、専門家への依頼費用として、一般的には数万円~数十万円程度を要します。
遺言執行者の選び方
1 遺言執行者になれる人

前提として、まずどのような人が遺言執行者になれるかを確認します。
遺言執行者は、相続発生時点において、未成年者および破産者でなければ、誰でもなることができます。
相続人の中から、遺言執行者を定めることもできます。
もっとも、遺言に記載されたとおりに相続関連の手続きをするためには、専門的な知識やノウハウが必要になることもあります。
そのため、法律上は未成年者・破産者以外は遺言執行者になることができますが、実務上は専門的知識・ノウハウを持っている者を遺言執行者にした方が良いといえます。
2 遺言執行者が行うこと
遺言執行者は、相続が開始されたらまずは速やかに遺言者の財産目録を作成して法定相続人に提示することが求められます。
遺言に記載されている財産は、遺言作成時に遺言者が把握していたものに過ぎませんので、相続開始時には変動が生じている可能性もあります。
そのため、相続財産の調査スキルが必要となります。
次に、相続財産を相続人、受遺者に引き渡す手続きをします。
預貯金であれば、金融機関において名義変更・払い戻しの手続きをします。
不動産においては、登記を行います。
これらの手続きも、相続に関する相当な知識を有していることが求められます。
専門家でなくても、理論上はできる手続きではありますが、時間を要してしまい遺産をなかなか取得できなかったり、先に相続登記を入れられてしまったりすることがあるなど、トラブルが発生する可能性もあります。
また、遺言に相続人の廃除、廃除の取消し、子の認知が記載されている場合、遺言執行者でなければこれを行うことができません。
これらも専門的な知識を要する手続きになります。
3 遺言執行者はどのように選べばよいか
以上のことからすると、遺言執行者は相続に関する法律に詳しい専門家を選ぶと良いといえます。
遺言執行者の候補としては、相続に詳しい弁護士が挙げられます。
遺言執行者は、遺言作成時に指定することが一般的ですので、遺言作成を依頼した弁護士を指定することも考えられますが、遺言作成時の弁護士を指定してしまうと、その後相続が発生した時に何らかの理由で当該弁護士が稼働できなくなっているという可能性もあります。
そこで、弁護士法人を指定しておくことで、同じ法人に属する弁護士が対応できるというメリットがあります。
遺言を作成するタイミング
1 遺言は早くから作った方が断然良い

結論から申し上げますと、遺言を作るタイミングは、早ければ早いほどよいです。
正確には、遺言を作る準備を、早いタイミングで始めることが大切です。
遺言は、遺言を書かれる方の重大な意思決定を記すものですので、すぐに満足できる内容を作ることができる性質のものではありません。
何度か書き、時間を置いてみて、さらに修正等をすることで、完成度の高い遺言ができあがります。
また、高齢になってから遺言を作成した場合には、相続発生後に問題が発生することもあります。
これらのことを考慮すると、できるだけ早いタイミングで遺言を作る方がよいといえます。
以下、詳細について説明します。
2 遺言作成のプロセス
遺言作成において、まず行う必要があるのは、遺言者の財産の洗い出しです。
預貯金、不動産、株式等、どのような財産を、どれだけ有しているのか、口座番号や地番等を確認し、できるだけ具体的に整理します。
できれば、通帳、登記、有価証券レポートなどの客観的な資料を用意します。
どのような財産があるかが分かればよいと思いがちですが、財産に関する正確な情報を遺言に記さないと、相続発生後の手続きに支障が生じる可能性があるためです。
次に、どの財産を誰に相続(遺贈)させるかを決めます。
財産の評価額等も考慮し、遺留分の問題を避ける考慮も必要になります。
これだけでも相当の時間と労力を要しますので、早めに遺言作成の準備を行う方がよいことが分かるかと思います。
そして、一旦上記の内容で、下書きを兼ねて自筆証書遺言を作ってみます。
自筆証書遺言であれば、費用等はあまりかかりません。
一度自筆証書遺言を書いてみてから、しばらく後に見直してみて、その時点で納得がいくようでしたら、専門家等に相談し、法的に問題のない形で清書するか、公正証書遺言を作成するという流れになります。
遺言を作成した後で財産の状況が変わったり、相続(遺贈)させる相手についての考えが変わったりした場合には、遺言を修正すればよいです。
時間的な余裕がないと、このようなことも行えないため、早めに遺言を作成した方がよいことになります。
3 高齢になってから遺言を作成する場合の問題点
遺言を作成する方が高齢になり、特に認知の衰えが始まってしまっていると、相続開始後に遺言の効力をめぐって争いが生じることがあります。
実は、遺言はその性質上、すべての相続人・受遺者に公平な内容で作ることが難しいため、不満を持つ相続人・受遺者が生じやすいのです。
そのため、遺言の作成能力に問題があったというきっかけを与えてしまうと、遺言無効確認訴訟を提起され、争いに発展する可能性が高まります。
こうなってしまうと、訴訟の決着がつくまで相続手続きを行うことが難しくなってしまったり、相続手続きをやり直さなければならなくなってしまったりするなど、大きな不利益が生じてしまいます。
まずは自筆証書遺言を書いてみる
1 遺言は何回か書いてみる必要がある

法律(特に家族法)の専門家でもない方が、いきなり完璧な遺言を書くというのは非常に難しいです。
遺言は、法律に従った形式を満たさなければならないという、法的側面の知識も大切ですが、そもそも何をどのように書いたらよいのか、イメージがつかないという方もいらっしゃるかもしれません。
なんとなく抽象的なイメージは湧いたとしても、いざ紙に書いてみようとすると、具体的な文字列は浮かんでこないものです。
その他にも、遺言に記載すべき財産がどのくらいあるのか、それらの財産の情報はどのように書けばよいのか、財産に関すること以外も書きたいが、書いてよいのかなど、疑問に思うことや迷うことはたくさんあるかと思います。
このような場合、はじめから専門家に依頼することもできますが、その前段階として、とにかく紙に書いてみるということをおすすめします。
はじめは、文字でなくてもよいです。
財産を箇条書きにして、相続させたい・遺贈したい方の名前と線で結んでもよいです。
これをすることで、抽象的であったイメージが具体化されてきます。
そのうえで、あまりこだわらずに、文章化していくというプロセスをとることが大切です。
専門家に依頼する場合であっても、ある程度の下書きがあった方が曖昧な部分も少なく、スムーズに遺言の作成を進めることができます。
2 自筆証書遺言を作る
では、上記1から一歩進んで、まずは自筆証書遺言を作成してみましょう。
自筆証書遺言は、すべて自筆で記載する必要があります。
例外として財産目録はパソコン等で作成してもよいとされますが、その際は各ページに署名押印をする必要があります。
財産が複雑でなければ、すべて自筆で書いてしまった方が、間違いが起きにくいかもしれません。
自筆証書遺言を作成する過程で、考えがまとまることもあります。
自筆証書遺言を作成したものの、すぐに別の考えが浮かぶこともあります。
そのような場合でもすぐに新しい遺言を作ることができるのが、自筆証書遺言の強みです。
公正証書遺言の場合でも、何度でも書き換えることはできますが、書き換えにかかる手間や費用は、自筆証書遺言の比ではありません。
内容が確定し、ご自身で納得のいく自筆証書遺言ができあがった段階で、公正証書遺言の作成を検討すればよいのです。
遺言の作成前に財産を見直しましょう
1 遺言の内容

遺言は、相続人間で相続財産をどのように分けるかについて、あらかじめ意思表示をしておくために作成します。
財産の分け方については、大きく分けて、2つの方法があります。
1つは、具体的に、どの相続財産を、誰が取得するかを記載するものです。
例えば、不動産は相続人Aが取得し、預貯金は相続人Bが取得するという形です。
もう1つは、相続財産について、分割の割合を指定するものです。
いずれにしても、遺言の対象とする財産を把握していないと、書くことができません。
そこで、遺言を作成するためには、まず遺言者の財産の整理が必要となります。
以下、代表的な財産について、整理方法を説明します。
2 預貯金
預貯金は、どの金融機関に口座を有しているかを調査する必要があります。
家の中にある預金通帳や、定期的に届く郵便物等を確認します。
預金口座は、意外と増えがちなものです。
ほとんど使っていない口座があることが判明した際は、預貯金を移した後に解約したりするなどして、単純化することも大切です。
3 不動産
お持ちの不動産を把握している場合には、売買契約書や権利証を確認します。
そして、これをもとに、登記事項証明書を取得しておくと、正確な情報をいつでも参照することができます。
お持ちの不動産について、よく分からなくなってしまった場合は、毎年届く固定資産税の通知書を確認します。
固定資産税通知書には、課税対象となる不動産の地番等の情報が記載されています。
4 その他の財産
高価な家財道具(特に再販価値がある時計、貴金属等)や、株式等の金融資産の残高および口座のある金融機関も、できる限り整理しておくとよいです。
家財道具は相続が発生した後の評価は難しいため、予め換金してしまうという方法もあります。
遺言作成前に準備すべきこと
1 遺言作成は準備が重要

遺言を書くことを思い立っても、すぐに書き始めることは得策ではありません。
特に自筆証書遺言の場合、表現が曖昧であったり、形式に不備があったり、筆跡や遺言者の遺言能力に疑いが生じるような要素があると、遺言者がお亡くなりなった後、遺言が無効になったり、相続人によって遺言の効力を争われたりすることがあり、遺言を書いた意味が全くなくなってしまいます。
そこで以下、遺言についての争いが発生しないようにするための注意点を説明します。
2 財産の調査を行いましょう
内容が曖昧な遺言書の多くは、財産についての記載が大雑把であるというケースです。
典型的な例としては、「〇〇県の土地は長男に」というものが挙げられます。
このような記載であると、どこの土地なのかが特定できず、他の相続人が争うきっかけを作ってしまうことがあります。
また、相続登記の際にも問題が生じることがあり、改めて遺産分割協議書を作らなければならず、このタイミングで争いが生じることもあります。
そのため、まずは遺言者の方がお持ちの財産を正確に調査することが大切です。
預貯金等であれば、通帳をお手元に揃え、銀行名、支店名、口座番号を正確に遺言書に書きます。
不動産は、少なくとも地番や家屋番号を記載します。
できれば、不動産の登記を取得し、登記に記載された内容を正確に書きます。
株式や投資信託等は、証券会社のレポート等を見ながら、証券会社名、口座番号、銘柄を正確に記載します。
3 形式面をチェックしましょう
特に自筆証書遺言を作る場合、形式のことをしっかりと意識する必要があります。
自筆証書遺言は、法律により、形式が厳格に定められているためです。
正しい形式で書かれていないと、原則として遺言は無効になってしまいます。
軽微な形式不備があっても無効にはならないと判断した裁判例もありますが、実際に軽微な形式不備があった場合、それが遺言を無効にするものであるか否かは、訴訟で争われた末に決まることです。
形式不備があったために訴訟問題に発展してしまうと、解決までに長期間を要してしまう可能性もありますので、そのようなことにならないよう、事前に弁護士に確認しながら、正しい形式で適切な遺言を作成することが大切です。
自筆証書遺言の注意点
1 自筆証書遺言について

自筆証書遺言は、法律で定められた遺言の一類型です。
遺言者が、財産目録を除き、すべてを自筆で書く必要がありますが、紙とペンさえあればいつでも作成ができます。
手軽に作成できるため、将来、公正証書遺言を作成することを見越して、下書きのような位置づけで作ってみるということも多いです。
もっとも、手軽に作れる半面、注意しなければならないこともあります。
自筆証書遺言の注意点について、主なものを以下で説明しますが、自筆証書遺言を作成される際には、弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。
2 形式不備に注意する
自筆証書遺言は、法律により、形式が厳格に定められています。
財産目録を除き、すべて自筆で書くことに加え、日付、署名、押印等が必要になります。
これらの形式不備があると、自筆証書遺言は原則として無効になってしまいます。
また、誤記(漢字を間違える、和暦と西暦を間違える等)があると、相続開始後に、相続人の間で遺言の効力についての争いが生じやすくなります。
争いが生じてしまうと、訴訟等になり、決着がつくまで遺産を動かすことが困難になってしまうこともあります。
3 筆跡に注意する
自筆証書遺言は、後で争いになりやすい傾向があります。
遺言というのは、通常、各相続人が平等になるように作ることは難しい部分があります。
程度の問題はありますが、誰かしらが不利になってしまいがちです。
そのような場合には、調停や訴訟が提起されることがあります。
そして、訴訟等においては、筆跡が被相続人のものと異なるという主張(つまり偽造されたという主張)がされることが多くあります。
間違いなく被相続人本人により書かれたものであることを示すため、できる限り、遺言と同じような緊張感で記載された文書(履歴書や目上に人に宛てた手紙など)のコピーを用意したり、遺言を書いている場面を録画したりするなどの対策が必要になります。
4 遺言能力も証明できるようにする
遺言は、遺言者がお年を召してから書かれることが多いです。
そのため、相続開始後に、遺言者において、遺言作成日時に遺言を書くことができる能力があったか否かの争いになることがあります。
これを防止するため、遺言を作成する日の直前等に、脳や身体機能に異常がない旨の医師の診断書を作成しておくといった対策が必要です。
5 保管方法にも注意する
自筆証書遺言を作成した後は、保管方法にも注意が必要です。
同居人の方に間違って捨てられてしまったり、内容を書き換えられてしまったりする等、紛失・偽造のリスクにも注意しなければなりませんし、遺言を作成したことを誰にも知らせないままにしてくと、相続後にその遺言が発見されないといったケースも考えられます。
そのため、自筆証書遺言の保管制度を利用するというのも一つの方法です。
参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度
遺言を作るメリット
1 相続争いの予防

遺言は、遺言者の保有している財産について、遺言者が亡くなった際、誰にどれだけのものを相続・遺贈するかを決めておく書面です。
遺言者が亡くなった場合、原則として、遺言に書かれている通りに財産が分配されますので、相続人同士で分け方を決める必要がなく、誰がどの財産をどれだけ取得するかという争いが生じません。
相続の紛争を防止できるという観点から、遺言を作成するメリットがあるといえます。
もっとも、特定の相続人にすべての財産を取得させるなど、極端に偏りがある内容であったり、財産の書き方が抽象的であったり、また、認知症が疑われる時期に書かれたものであったりすると、かえって遺留分侵害額請求訴訟や遺言無効確認訴訟を提起され、争いの火種になることもありますので注意が必要です。
2 財産の整理ができたり、生前対策のきっかけとなることも
遺言の作成を検討する際、まず初めに行うことは、遺言者の財産の整理です。
どのような財産があるかが分からないと、誰にどの財産を残すかの検討ができないためです。
預貯金、不動産、有価証券、その他価値のある動産等、相続の対象になる財産の一覧と、それらの財産の根拠となる資料(預金通帳、不動産登記事項証明書、有価証券レポート等)を集めます。
また、相続財産ではありませんが、死亡保険金等を受け取る相続人がいる場合、その情報も把握しておくとよいです。
一通り財産の状況が把握できましたら、大体の評価額を計算します。
これは、複数の人で相続財産を分ける場合、遺留分の侵害等を防ぐために行います。
このように、遺言を作成するにあたって財産の把握や整理ができることもメリットのひとつかと思います。
また、遺言者が所有している財産を見直すことで、税金がどれくらいかかるかの目安が分かり、そこから生前対策を行うきっかけとなる場合もあります。
例えば、遺言者が自宅土地建物を所有している場合は、同居している配偶者や子に相続させる旨を遺言に記載することで、将来相続が発生した際に相続税を低減することができる場合があります。
他にも、多額の現金・預貯金が存在する場合、生前から贈与税がかからない範囲内で子などに贈与しておくといった対策を検討する機会にもなるといえます。
遺言の種類とそれぞれのメリット・デメリット
1 遺言の種類

遺言にはいくつかの種類があります。
実務上、多く用いられるものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
どちらも遺言としての効力に差はないので、それぞれのメリットとデメリットを考慮しながらどちらで作成するかを選択することになります。
どちらで作成するのがよいか迷ったら、弁護士にご相談ください。
2 自筆証書遺言のメリットとデメリット
⑴ メリット
自筆証書遺言は、遺言者がすべて自筆で書く形式の遺言書です(財産目録を除く)。
極論すれば、紙とペンさえあれば、いつ・どこでも作成することができるため、非常にコストを下げることができます。
自分だけで作ることができますので、関係者と連絡を取り合ったりする必要もありません。
また、一度作った後で考えが変わったり、財産の状況が変化したりしたとしても、すぐに作り直すことができます。
⑵ デメリット
遺言は法律により形式が厳格に定められています。
法律の専門家でない方が独学で書くと、形式不備が生じてしまい、遺言としての効力がなくなってしまうことがあります。
保管場所にも注意が必要です。
紛失や滅失をしてしまう可能性があるため、安全な場所に保管する必要があります。
また、相続に関する事案を扱っていると、自筆証書遺言が発見された場合、相続人の一部が遺言無効確認訴訟を提起することが多く見受けられます。
自筆証書遺言は、作成された時の遺言者の認知状態が不明であることや、そもそも本当に遺言者が自身の手で書いたか否かが客観的に証明できないことが多いためです。
そのため、遺言の内容に偏りがあり、不利な条件となってしまっている相続人が、とりあえず無効確認訴訟を提起するということがあります。
3 公正証書遺言のメリットとデメリット
⑴ メリット
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家によって作成されます。
そのため、基本的に形式の不備が生じることがなく、形式の問題で遺言が無効になることがありません。
また、遺言者は下書きを作成すれば、これを公証役場で清書してくれますので、自筆で作成する必要がありません。
身体的な事情により、文字を書くことが困難な方でも作成できます。
公正証書遺言を作成する際は、公証人が遺言者の面前で内容を確認します。
この時に、認知状況等に問題があると判断されれば、原則として遺言は作成されません。
逆に言えば、公正証書遺言が作成されているということは、認知状態等(遺言能力)に問題がないと公証人が判断していることになります。
そのため、後日偽造や遺言能力について、争われる可能性を大きく減らすことができます。
⑵ デメリット
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、公証役場で公証人に依頼する必要がありますので、そのやり取りをする手間や数万円~数十万円程度の手数料がかかります。
なお、公証人は遺言の内容のチェックをしてくれるわけではありませんので、どのような内容にしたら後々揉めにくいかについてアドバイスが欲しいといった場合には、別途、弁護士に相談をする必要があります。
また、公証役場とのやり取りや遺言内容の下書きについて、弁護士に依頼した場合も、手数料が生じます。
遺言作成を弁護士に相談すべき理由
1 弁護士だからこそできること

遺言作成に関与する専門家は、弁護士以外にも、司法書士や行政書士等がいます。
これらの専門家の中で、あえて遺言作成を弁護士に相談すべきである理由は、弁護士だからこそできることがあるからに他なりません。
弁護士は、法律の専門家として、あらゆる紛争案件に対応しています。
このため、遺言作成に当たっても、過去の紛争事例を参照し、将来、紛争が生じないようにするためにはどのような遺言を作成すべきかについて、アドバイスをすることができます。
このように、将来の紛争を避けるためのアドバイスを得た上で遺言を作成することができるのが、遺言作成を弁護士に相談すべき理由になります。
2 将来の紛争を避けるためのアドバイスの例
遺言についての紛争は、多くの場合、遺言無効確認か遺留分侵害額請求のいずれかになります。
したがって、遺言を作成するに当たっては、どのようにすれば遺言無効確認や遺留分侵害額請求等の紛争を避けることができるのかを検討するのが望ましいです。
ここでは、遺言無効確認の紛争を避けるためには、どのような対策を行えばよいかについてのアドバイスの例を紹介したいと思います。
遺言無効確認の主張は、①遺言の内容が不明確であり、合理的に解釈することができないと考えられる場合、②遺言を作成した時点で、遺言者が判断能力を失っていた可能性がある場合、③遺言の筆跡が本当に遺言者のものであるかどうかが分からない場合になされます。
遺言の内容が不明確であるとの主張がなされることを避けるためには、一義的に明確な遺言を作成する必要があります。
また、遺言を作成した時点で判断能力を失っていたとの主張がなされることを避けるためには、医師の診断書を取り付ける、公正証書により遺言を作成する等の対策が考えられます。
遺言の筆跡が本当に遺言者のものかどうか分からないとの主張がなされることを避けるためには、遺言書に実印を押印し、印鑑証明書を添付する、遺言作成時の録画等を残す、公正証書により遺言を作成する等の対策が考えられます。
このように、遺言作成時に必要な対策を行っておくことにより、将来、遺言についての紛争が発生することを避けることができます。
3 遺言についてのご相談
当法人には、遺言をはじめ、相続の案件を集中的に扱っている弁護士がいます。
将来、遺言についての紛争が発生することを避けるためにはどのような対策が考えられるかについても、助言をさせていただいています。
柏やその周辺にお住まいで、遺言についてお困りのことがあれば、当法人にご相談ください。