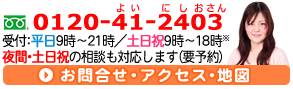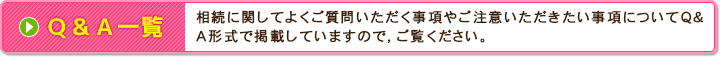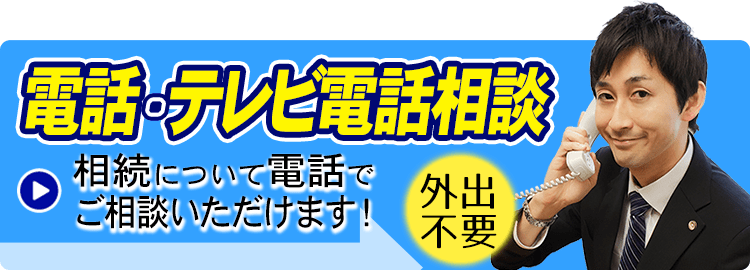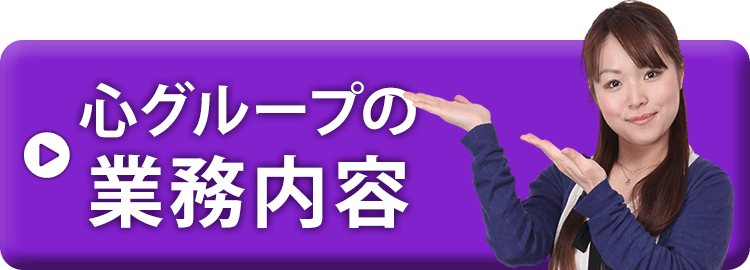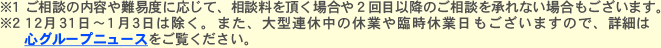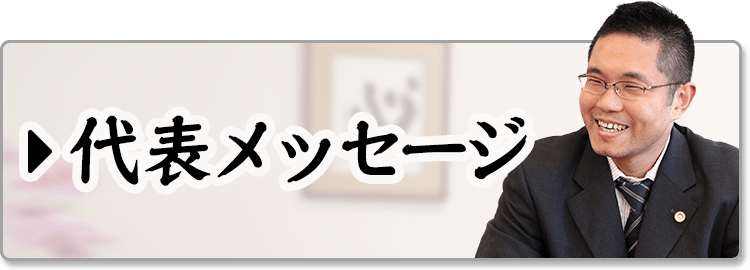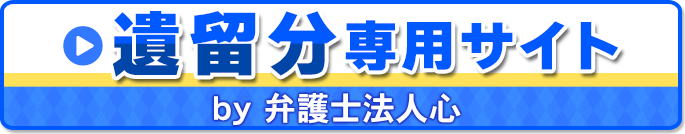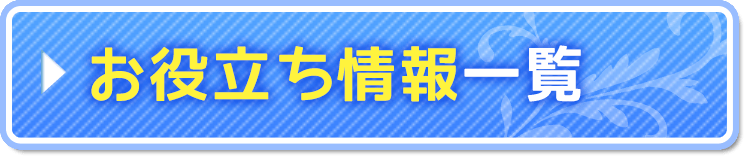法定相続分の計算
1 法定相続分とは
法定相続分は、法律で定められた遺産の分け方の基準です。
遺産分割、相続税額の計算、遺留分侵害額の計算など、様々な場面で大きな意味を持ってきます。
法定相続分は、
・相続人の人数
・被相続人との関係
・相続放棄をした人の有無
等により法律で決まります。
この法定相続分は遺産分割の際に、分割の仕方を定める際の目安になります。
また、相続税額の計算においては、一旦法定相続分で各相続人で分割したと仮定して納税総額を算出します。
遺留分侵害額の計算においても、相続人の遺留分割合を算出するために法定相続分による割合が必要になってきます。
このように法定相続分とは、相続の手続きにおいては不可欠な基準となります。
そして、法定相続分に特別受益や寄与分といった個々のご家族ごとの事情を踏まえて、実際に相続する金額が決まります。
これを具体的相続分といいます。
「生前贈与を受けた相続人がいる(=特別受益)」「相続人の1人が献身的な介護をした(=寄与分)」といった事情は具体的相続分の計算の際に考慮されるため、法定相続分の計算の際には考慮されません。
2 法定相続分の計算方法
法定相続分は、誰が相続人になるかによって計算方法が変わります。
① 子供が相続人になる場合
亡くなった方に子供や孫がいる場合は、子供や孫が相続人となります。
このとき、親や兄弟が存命でも、子供がいる以上、相続人とはなりません。
この場合、相続分は
配偶者:1/2
子供全員の相続分の合計:1/2
となります。
そして、子供同士は平等であるため、この1/2を子供の人数で割ることとなります。
たとえば、奥さんと子供が3人いる場合は、配偶者1/2、子供が各1/6となります。
なお、配偶者が先に亡くなっている場合は、1/1(100%)の相続分を子供の人数で割ることとなります。
②親が相続人になる場合
亡くなった方に子供や孫がおらず、親が存命の場合は、親が相続人となります。
この場合、相続分は
配偶者:2/3
両親の合計:1/3
となります。
配偶者が先に亡くなっている場合は、子供のときと同じです。
③兄弟が相続人になる場合
子供や孫、両親もいない場合には、兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。
この場合、相続分は
配偶者:3/4
兄弟姉妹の合計:1/4
となります。
そして、兄弟姉妹も平等であるため、1/4(配偶者がいない場合は1/1)を兄弟姉妹で割ります。
参考リンク:国税庁・相続人の範囲と法定相続分
3 代襲相続の際の注意点
亡くなった人の子供が先に死亡していた場合、その子供の子、すなわち孫が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
ただし、1つ注意しなければいけない点として、代襲相続が発生したときは同じ孫でも相続分が違う可能性があります。
たとえば、死亡時にその2人の子AとBが死亡していた場合に、子Aの子供A1と子Bの子供B1、B2、B3が代襲相続をした場合、その相続分は
孫A1:1/2
孫B1〜B3:各1/6
となります。
孫が4人だから全員1/4とはならないので注意が必要です。
また、子が親の相続について相続放棄をしていた場合には、子の子供(つまり孫)は、代襲相続をすることができません。
なぜなら、相続放棄とは相続時に遡って一切の遺産を放棄する手続きですので、子が相続放棄をしていた場合には、その子は親の相続発生時点から相続人ではなかったことになりますので、そもそも孫も被相続人の相続権を持っていないことになるからです。
相続開始後に親の入っていた生命保険を調べる方法 農地を相続する場合の注意点